国際協力の仕事には、開発コンサルタントをはじめ、大手・中堅ゼネコン、商社、メーカーなど、数多くの民間企業が参画している。その中でも、国際協力事業のプランニングから実施段階、完了後の評価やモニタリングまで、一貫して相手国に協力していくのが開発コンサルタントである。(国際協力ガイド2006)
以下は、「国際開発コンサルタントのプロジェクト・マネジメント コーエイ総合研究所 2003」をもとに筆者が加筆した。
農村開発、漁村開発、教育、商業、観光、水資源開発、電力・エネルギーなど多岐にわたる。その中でも運輸・交通が25%程度の割合を占め、次いで電力・エネルギー、水資源開発の割合が高い。これは1件あたりの規模が大きいことが理由として挙げられる。
また、近年、環境分野での実績が伸びてきていることも注目に値する。
アセアン諸国を中心とするアジア地域の比率が6割以上と大部分を占める傾向が続いており、次いでアフリカ、中南米となっている。
JICAやJBIC等の日本政府による二国間援助事業が8割以上を占めている。ADB、WB等の国際機関や対象途上国政府の資金による事業は1割程度にとどまる。なお、クライアント別で見ると、借款の場合は本体事業のクライアントは途上国政府となるため、割合は大きく変わる。
事業はおおよそ次の段階に分かれる。
調査・計画段階はJICAによる技術協力、それ以降から建設段階まではJBICによる有償資金協力と自国資金、運営・維持段階は自国資金により行われるのが通例である。
調査・計画段階 発注者は相手国政府の要請を受けたJICAとなることが多く、コンサルタンは調査・計画業務の実施者である。
また、JICAが発注者の場合の入札手順を下図に示した。
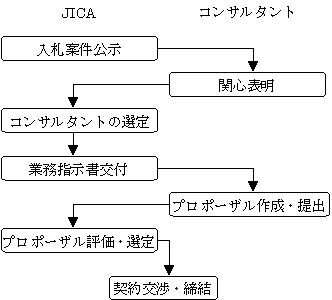
発注者は途上国政府となることが多く、コンサルタントは設計業務の実施者である。
建設準備段階コンサルタントは発注者が行う公示入札および契約交渉・締結のための支援を行う。つまり、コンサルタントは発注者をサポートする立場になる。
建設段階コンサルタントは発注者業務を支援したり、工事請負業者との間で設計の変更、またクレームに対応する中立的な裁定者の立場をとる。
運営・維持段階コンサルタントは発注者を支援したり、要請に応じて、調査等を行う。